「日本酒は水が大切」って話、誰しも一度は聞いたことがありますよね。
ただこの話がひっくり返されるような話が出てきているようです。

近年、日本酒造りの技術は目覚ましい進歩を遂げており、水以外の要素の重要性が以前にも増して注目されているのをご存知ですか?
これには私もびっくりして、調べてみました!
まず水以外の要素の重要性を見る前に、日本酒の製造方法からおさらいしておきます。
日本酒の製造方法
日本酒が私たちの手に届くまでには次のような9つの工程があります。
1. 原料処理
- 精米(せいまい): 玄米を削り、糠(ぬか)や不要なタンパク質、脂肪を取り除く工程です。精米歩合(削り残った米の割合)によって、酒の味わいが大きく変わります。
- 洗米(せんまい)・浸漬(しんせき): 精米された米を洗い、表面の糠を完全に洗い流します。その後、米に吸水させるために水に浸します。浸漬時間は、米の種類や精米歩合、季節などによって細かく調整されます。
- 蒸米(じょうまい): 水に浸漬させた米を蒸気で蒸します。蒸し加減は、麹造りや醪(もろみ)の発酵に大きく影響するため、非常に重要な工程です。
2. 麹造り(こうじづくり)
- 蒸米の一部を使い、麹菌(主に黄麹菌)を繁殖させる工程です。
- 蒸米に種麹(たねこうじ)を振りかけ、温度や湿度を管理しながら約2日間かけて麹を育てます。
- 麹は、米のデンプンをブドウ糖に変える酵素を作り出す役割を担い、日本酒の甘味の元となります。
3. 酒母造り(しゅぼづくり)
- 酵母を純粋に培養し、健全な発酵を促すための準備段階です。
- 少量の蒸米、麹、水に、培養された酵母を加え、約2週間かけて酵母を増やします。
- 酒母は、醪の健全な発酵を導くための「酛(もと)」とも呼ばれます。
4. 醪造り(もろみづくり)
- 酒母に、残りの蒸米、麹、水を数回に分けて加え、発酵させる工程です(三段仕込みが一般的です)。
- 酵母がブドウ糖をアルコールと炭酸ガスに分解し、日本酒のアルコール分と独特の風味が生まれます。
- 醪の期間は約2~4週間で、温度管理などが非常に重要になります。
5. 搾り(しぼり)
- 発酵を終えた醪を搾り、液体(日本酒)と固形物(酒粕)に分離する工程です。
- 昔ながらの槽(ふね)搾りや、機械を使った自動圧搾機など、様々な方法があります。
6. 滓引き(おりびき)
- 搾られたばかりの日本酒には、まだ細かい浮遊物(滓)が含まれているため、静置して滓を沈殿させる工程です。
7. 火入れ(ひいれ)
- 日本酒の品質を安定させるために行う加熱処理です。
- 酵素の失活や、火落菌(ひおちきん)と呼ばれる雑菌の繁殖を防ぐ目的があります。
- 通常、貯蔵前と瓶詰前の2回行われることが多いですが、生酒(なまざけ)は火入れを行いません。
8. 貯蔵(ちょぞう)
- 火入れを終えた日本酒を、タンクや瓶などで一定期間貯蔵し、熟成させる工程です。
- 貯蔵期間や温度によって、日本酒の味わいが変化します。
9. 瓶詰(びんづめ)・出荷
- 貯蔵・熟成された日本酒を瓶に詰め、ラベルを貼って出荷されます。
- 瓶詰めの際にも、再度火入れを行う場合があります。
以上が日本酒製造の大まかな流れです。実際には、酒蔵や目指す酒質によって、細かな工程や管理方法が異なります。
このようにして作られる日本酒の約8割は水でできており、使用する水の種類や質によって、日本酒の味わいが大きく左右されます。
水が日本酒に与える影響
- 仕込み水としての影響:
- 硬水: ミネラル分(特にカルシウムやマグネシウム)を多く含む硬水は、酵母の活動を活発にし、発酵を促進するため、キレのある辛口の日本酒になりやすいと言われています。灘の「男酒」と呼ばれる日本酒には硬水が使われることが多いです。
- 軟水: ミネラル分が少ない軟水は、酵母の活動を穏やかにするため、まろやかで優しい甘口の日本酒になりやすいと言われています。伏見の「女酒」と呼ばれる日本酒には軟水が使われることが多いです。
- 仕込み水に含まれる鉄分やマンガンは、日本酒の色を悪くしたり、香りを損なったりするため、極めて低い含有量であることが求められます。酒造用水は、水道水よりも厳しい基準が設けられています。
- 洗米・浸漬水としての影響:
- 精米された米は、蒸される前に洗米・浸漬されますが、この工程で米が吸収する水によって、その後のもろみの質に影響が出ると言われています。
- 割水(加水)としての影響:
- 搾られたばかりの日本酒(原酒)はアルコール度数が高いため、出荷前に水を加えて調整することがあります。この割水に使用する水の質も、最終的な日本酒の味わいやバランスに影響を与えます。
- 酒蔵の立地:
- 良質な水を求めて、昔から酒蔵は名水の地に建てられることが多いです。
このように、日本酒造りの様々な工程で水は欠かせない存在であり、その質が日本酒の出来を大きく左右するため、「日本酒は水が大切」と言えるのです。
そして、、、
土地に合った製法は日本酒造りにおいて極めて重要です。特に風土の観点から見ると、土地によって異なる水質は、その土地ならではの日本酒を生み出すための根幹となります。ミネラル分の含有量の違いは、酵母の生育や働きに直接的な影響を与えます。例えば、硬水に多く含まれるミネラル分(特にリン酸やカリウム)は、酵母の栄養となり、活発な発酵を促すため、力強く辛口な酒質になりやすい傾向があります。一方、軟水はミネラル分が少ないため、酵母の働きが穏やかになり、きめ細やかで優しい甘口の酒質になりやすいと言われています。
このような水質の違いに対応するため、各地の酒蔵では長年の経験と工夫に基づいて、その土地の水に最適な酵母の選択、麹の造り方、発酵の温度管理などの製法を発展させてきました。また、その土地の気候風土(寒冷な気候は低温での長期発酵に適している、温暖な気候は速醸に適しているなど)、入手しやすい米の種類、そして地域の食文化との調和なども、その土地ならではの製法が生まれる背景となります。
例えば、ご指摘のあった**広島の灘(西条)は、全国的に見ても珍しい軟水の名水に恵まれた地域です。この軟水を生かすため、広島の酒蔵は「軟水醸造」**という独自の技術を磨き上げてきました。軟水では酵母の活動が穏やかになるため、より丁寧に時間をかけて発酵させる技術や、軟水でも十分に力を発揮する独自の酵母の開発などが進められてきました。その結果、西条の日本酒は、まろやかで口当たりの優しい、上品な味わいが特徴となっています。
対照的に、兵庫の灘は硬水である宮水が有名であり、この硬水を用いることで、**力強くキレのある辛口の「男酒」**として知られる日本酒が造られてきました。このように、同じ「灘」という名前を持ちながらも、水質の違いが酒質の違い、そしてそれに合わせた製法の違いを生み出している好例と言えます。
さらに、土地によっては、高温多湿な気候に対応するための速醸技術が発展したり、特定の土地で栽培される酒米の特性を最大限に引き出すための特別な製法が生まれたりすることもあります。
このように、土地の風土、特に水質は、その土地の日本酒の特性を決定づける重要な要素であり、それぞれの土地の環境に合わせて、最適な製法が長年にわたり育まれてきたのです。現代においても、気候変動や原料の変化に対応しながら、土地の風土を生かした個性豊かな日本酒造りが続けられています。
しかし、、、
- 酵母の開発: 各酒蔵や研究機関で、多様な香味特性を持つ酵母が開発されています。これにより、かつては水質によって左右されていた酒質の一部が、酵母の選択によってよりコントロールできるようになってきています。特定の水質でしか育ちにくいと考えられていた酵母が、培養技術の向上によって他の水質でも力を発揮する例も出てきています。
- 麹の重要性の再認識: 麹は日本酒の味わいを決定づける非常に重要な要素であり、その製造方法や使用する麹菌の種類によって、最終的な酒質は大きく変化します。近年、麹造りの技術がより深く研究され、水の特性以上に麹の持つポテンシャルが重視される傾向があります。
- 米の品種改良と特性の理解: 酒造好適米の品種改良が進み、それぞれの米が持つ特性を最大限に引き出すための仕込み方法が研究されています。米の溶けやすさやアミノ酸の出やすさなどが、水の特性以上に酒質に影響を与える場合もあります。
- 発酵制御技術の進化: 温度管理や発酵経過のモニタリング技術が向上し、より精密な酒造りが可能になっています。これにより、水質による影響を受けやすい発酵過程を、技術によってある程度コントロールできるようになってきています。
- 職人の経験と技術: 最終的な日本酒の品質は、杜氏や蔵人の長年の経験と培われた技術に大きく左右されます。同じ水を使っても、職人の腕によって全く異なる酒が生まれることは珍しくありません。
もちろん、水が日本酒の大部分を占める原料であることに変わりはなく、その質が最終的な酒質に影響を与えることは否定できません。しかし、現代の日本酒造りにおいては、高品質な米、優れた酵母、高度な麹造り、精密な発酵管理、そして何よりも職人の卓越した技術といった、水以外の要素も非常に重要な役割を果たしており、これらの要素を組み合わせることで、水の持つ特性を最大限に引き出したり、あるいは水の弱点を補ったりすることも可能になっています。
したがって、「日本酒は水が大切」という言葉は依然として重要ですが、現代においては、「日本酒は、良質な水、米、麹、酵母、そしてそれを操る職人の技術、これらの全ての要素がバランス良く組み合わさることで、素晴らしい酒が生まれる」 と捉える方が、より実情に即していると言えるかもしれません。水は依然として不可欠な要素ではありますが、他の要素の進化と重要性の高まりによって、その絶対的な重要性は相対的に変化してきていると言えるでしょう。
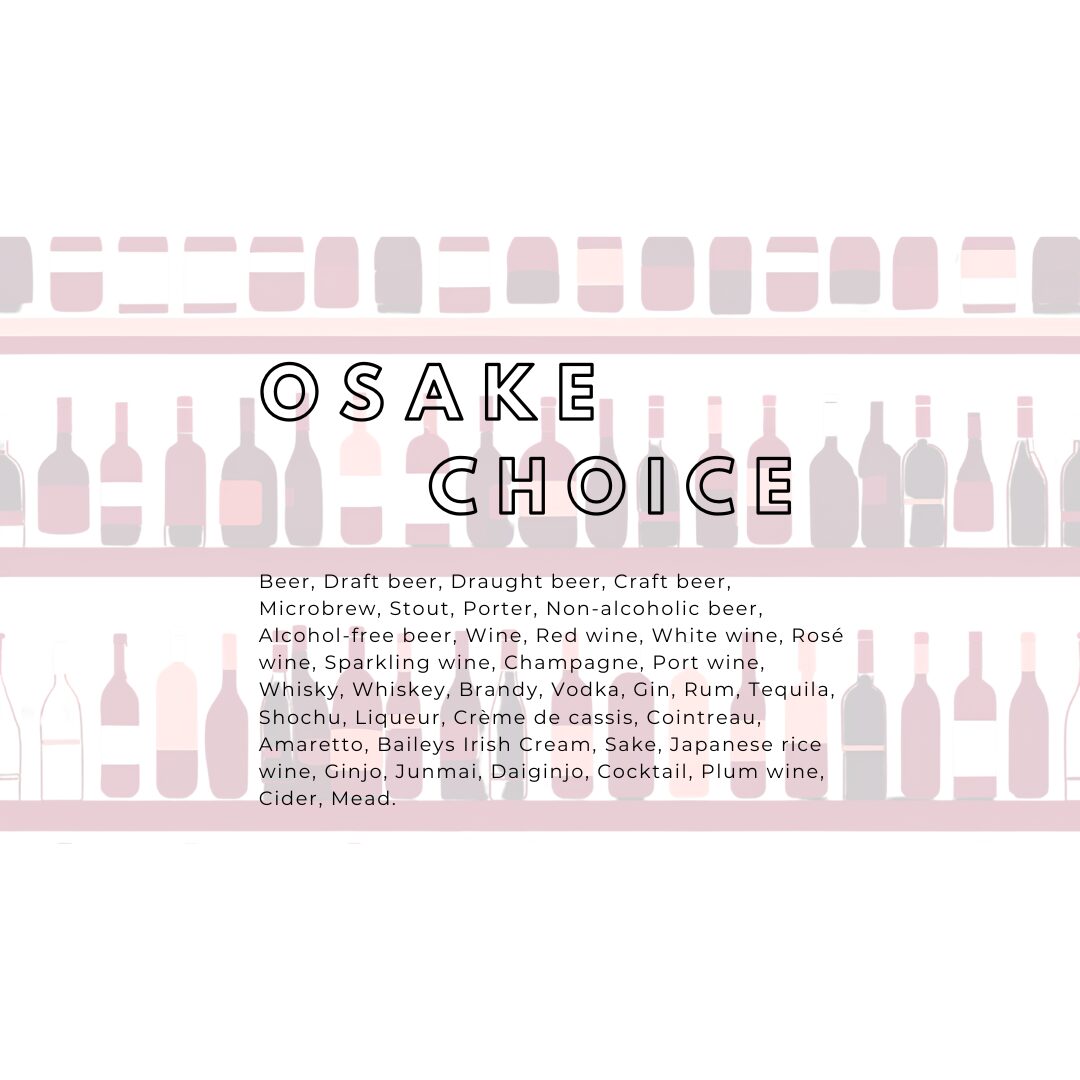


コメント